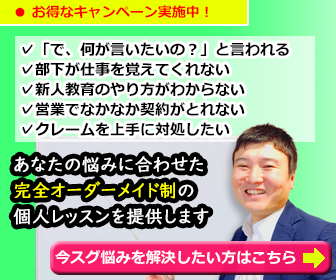話し方トレーニングとは?
話し方トレーニングとは、声を出す練習や滑舌を鍛えるトレーニングだけではなく、相手にわかりやすく伝えるために「思考を整理し、順序立てて話す力」を養うものです。一般的な話し方教室では、発声やスピーチの型に重点が置かれることが多いですが、それだけでは「知っているのに使えない」という悩みに直面する方も少なくありません。
私たち株式会社あたまが運営する話し方教室では、こうした表面的な技術だけではなく、頭の中を整理して「相手が聞きたい順番で伝える」ことに重点を置いています。そしてこの記事では、そんなあたま式のノウハウをすべて公開し、誰でも実践できる形で紹介していきます!
それではさっそく、話し方トレーニングで得られる効果から見ていきましょう。
話し方トレーニングで得られる効果
「話し方を変えたい」と思ったとき、私たちはつい表面的な“話し方の技術”ばかりに目を向けがちです。 でも実際には、話す順番や意図の整理、言葉の選び方といった「話す前の準備」によって、得られる効果は大きく変わります。
ここでは、実際に話し方トレーニングを受けた方々が感じた変化の中でも、特に多くの人に共通していたものをご紹介します。
自信がついて、人前で堂々と話せるようになる

話し方に悩んでいる人の多くは、うまく話せない理由を「性格」や「メンタル」のせいだと思い込みがちです。
ですが実際には、うまく話せない原因の多くは、話す内容が頭の中で整理できていないことにあります。
何を、どの順番で、どう伝えるか。この設計があいまいなままだと、話し始めてすぐに迷子になります。
すると、言葉に詰まったり、言い直したりする場面が増えていき、「やっぱり自分は話すのが苦手だ」と思い込んでしまうのです。
まずは、話す前の準備を整えること。
それに加えて、声の出し方や滑舌のトレーニングを組み合わせていくことで、「伝えられた」という感覚が少しずつ積み上がっていきます。
「声が前より出るようになった」
「話す前に頭の中が整理されていると、こんなにも落ち着いて話せるのかと思った」
そんな変化が、話すことへの自信を育ててくれます。自信はできるようになったという実感の中で、自然と芽生えていくものです。
信頼を得られることでビジネスの成果が変わる

ビジネスの現場では、「誰が言うか」と同じくらい、「何をどう伝えるか」が重視されます。どれだけ真剣に話しても、話の順序がバラバラだったり、結論が見えにくかったりすると、内容そのものの信頼性まで疑われてしまうこともあるのです。
話し方トレーニングでは、話の構造を整理する力も自然と養われていきます。 結論を先に述べる習慣や、理由→具体例→まとめという順序を体にしみ込ませていくことで、相手に「わかりやすい」「筋が通っている」という印象を与えられるようになります。
話し方が変わると、相手の理解が深まるだけではなく、信頼そのものが積み上がっていきます。 その積み重ねが、プレゼンの説得力や会議での発言力、日々の評価にもつながっていくのです。
人間関係がスムーズになり、誤解やすれ違いが減る

話し方トレーニングを積み上げると、 「最近、人とのやり取りが前よりラクかもしれない」 といった実感が、日常のあちこちに現れてきます。
それまで感じていたすれ違いのような違和感が、いつの間にか減っている。 「伝えたつもりなのに、なぜか怒られる」 「なんでそんなふうに受け取られたんだろう」 そういった事象の原因が、実は話し方にあったと気づく人も少なくありません。
話し方トレーニングでは、頭の中で言いたいことを整理し、相手にとって理解しやすい順番で伝える力が育ちます。 すると、余計な誤解を招く言い回しが減ったり、感情的に相手に言葉をぶつけるといったりしたことが無くなります。
また、「ちゃんと伝わっている」という実感があると、人と話すことへの不安も薄れます。 その安心感が、会話のトーンや距離感にも影響を与え、結果として人間関係がスムーズになっていくのです。
初心者でもできる基本トレーニング4ステップ
話し方トレーニングでどんな変化が起きるのかがわかったところで、いよいよ、あたま式の話し方トレーニングについて紹介します。
まずは初心者でもすぐに取り組める基本的なトレーニングです。どれも特別な道具や準備はいりません。話すことに苦手意識がある方でも、今日から実践できる内容ばかりなので、ぜひお試しください。
step1.呼吸を整えて、安定した話の土台をつくる
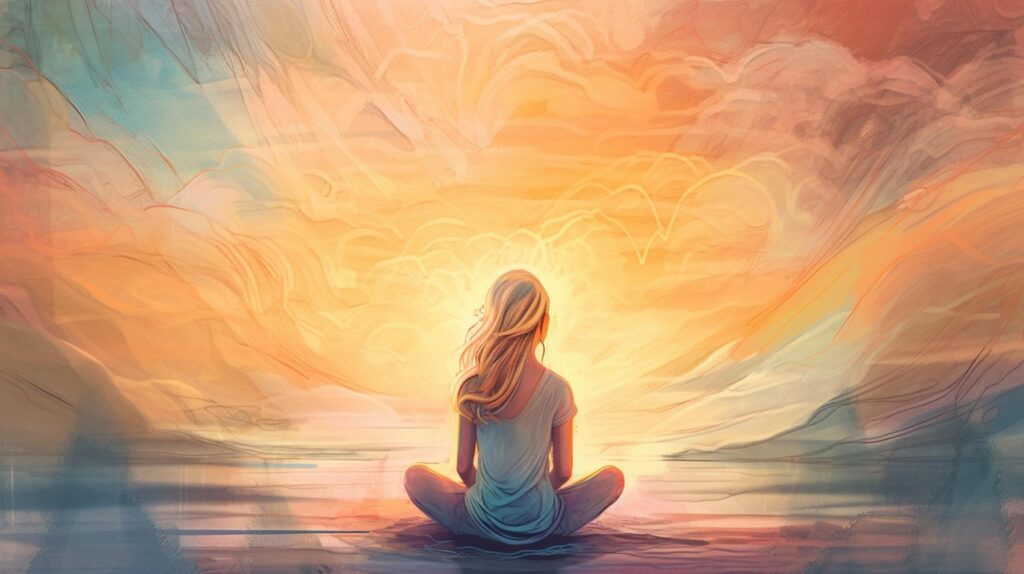
話し方トレーニングの本質は、「思考を整理し、順序立てて話す力」を養うことです。しかし、いくら内容を整理しても、音声として相手にしっかり届かなければ意味がありません。
そこで重要になるのが、呼吸の安定です。せっかくの論理的な話も、声が小さかったり息が切れていたりすると、説得力が半減してしまいます。逆に、無理なく通る声で話せるだけで、聞き手の集中力や受け取り方が大きく変わるのです。
「声が通らないのは生まれつき」と思っている人も多いかもしれませんが、これはトレーニングで十分に変えられます。たとえば、1日数回だけでも、腹式呼吸をしてみると、息の安定感が育っていきます。
腹式呼吸を意識するだけで声の質が大きく変わります。慣れてきたら、さらに「リラックスして喉の奥を開ける」「なるべく少ない息に声を乗せるようにする」といったようなことも挑戦してみてください。
step2.滑舌・スピードを見直して、伝わりやすい言葉にする

呼吸が整ってくると、話すこと自体に余裕が出てくると思います。ただ、それでもなぜか相手が聞き返してくる。冷静なつもりなのに、急かしているように聞こえてしまう。そういったことがあるかもしれません。
これらは、滑舌の甘さやスピードの乱れが原因です。
滑舌や話すスピードは、声の大きさ以上にその人の印象を左右します。声が大きく、話す内容が論理的でも、そもそも聞き取りづらいといったことが起こっては意味がないですよね。
そこで、1日1分でもいいので「外郎売」やニュース原稿の読み上げをしてみてください。ゆっくり、はっきり声に出すだけでも、言葉の明瞭さは確実に変わっていきます。録音して自分のスピードを客観的に把握するのも有効です。
step3.話の型を体に覚えさせる

呼吸、声、滑舌、スピードといった相手の耳にダイレクトに届くトレーニングが完了したら、「話す内容の順序」や「構成そのもの」に意識を向けましょう。
とはいえ、いきなり型を用意して、その通りに話すというのはなかなか難しいかもしれません。そこで、文章の読み上げを通じて構造的な話し方の型を身につけるトレーニングをご紹介します。
多くの人は、話すときに頭の中でゼロから文章を組み立てようとします。しかしその場で言葉を考えると、どうしても話の順序が崩れたり、内容が散らかったりしやすくなります。そこで、あらかじめ構造が整理された文章を声に出して読むことで、「話の順序」を体感的に理解し、自然と自分の話し方にも反映されるようになります。
「ただ読むだけで身につくのか」と疑問に感じるかもしれませんが、文章には結論と理由、具体例や補足といった情報の並び方が明確に存在します。この順番を音読で繰り返すことで、聞き手にとって理解しやすい話し方の土台が、無意識のうちに育っていきます。
教材としては、新聞の社説やビジネス記事など、構成が明快な文章がおすすめです。最初はゆっくりで構いません。内容の意味を追いながら声に出すだけで、情報の順序やつなぎ方が感覚的に身についていきます。
step4.PREP法で「伝わる話し方の型」を身につける

文章の読み上げで「話の順序」に慣れてきたら、いよいよ自分の言葉で組み立てて話すステップです。そこで役に立つのが、話し方の型として有名なPREP法です。
PREPは、結論(Point)→ 理由(Reason)→ 具体例(Example)→結論(Point)という順番で話す方法。聞き手が「何の話か」を最初に把握できるので、話の意図が伝わりやすくなります。
シンプルな構造ですが、いざ使ってみるとかなり難しさを感じるはずです。
「話しているうちに、話が横道に逸れてしまう」「結論がわからず、結局ダラダラと経緯から話してしまう」慣れるまではこんな状態になってしまうかもしれません。
そこで、いきなり話すのではなく、最初は紙に書きながら、簡単なテーマで順番通りに文章を組み立てるトレーニングから始めてみましょう。
たとえば、「自分の好きな映画」「おすすめのランチのお店」など、身近なテーマを使ってPREP法で文章を組み立てる練習をします。
「私はタイタニックが好きだ。なぜなら…」「私がおすすめしたいランチは、渋谷の●●です。なぜなら…」のように文章を作成してみましょう。
1日5分でできるセルフ練習法

さらに毎日PREP法をトレーニングしたい方に、とっておきの方法があります。それは、1日5分でできる「ひとこと日記」です。
やり方はとてもシンプルです。まず、その日を一言で表すならどんな日だったか?と自分に問いかけ、それを一行で書き出します。たとえば、「今日は散々な日だった」「とても嬉しい日だった」といった具合に、ひとことで表現します。
次に、その理由を簡単に言葉にします。「なぜ散々だったのか?」「何が嬉しかったのか?」を、2行目・3行目に書いてみる。この流れだけで、自然とPREP法の順序(結論→理由→具体例)に近い形ができあがります。
この練習は、考えを整理する習慣づけとしても非常に効果的です。話す前に「何を伝えたいか」と「なぜそう思ったのか」を頭の中で組み立てる力が養われていきます。また、毎日続けることで、感情や出来事を客観的に捉える視点も身につきます。
少しずつでも書き続けることで、「話す前に整理する」ことが当たり前になり、実際の会話やプレゼンでもスムーズに言葉が出てくるようになるでしょう。
話し方の「再現性」は仕組みでつくれる
基本トレーニングの4ステップを通じて、話の構成や相手とのやりとりが整ってきた方の中には、「うまくいくときと、うまくいかないときの差がある」と感じ始める人もいます。実はここからが、話し方の“再現性”を意識する大事なステップです。
再現性とは、「どんな場面でも安定して話せるようになる」ということ。緊張した日でも、話す相手が変わっても、自分なりの話し方の土台があることで、大きく崩れずに伝えられるようになります。これは一部の人のセンスではなく、日々の中に仕組みとして取り入れることで、誰にでも身につけることができます。
たとえば、毎朝3分で「今日話すべきことをPREPで整理する」習慣をつくる。あるいは、人の話を聞くときに「この人は今、理由を話しているのか、具体例なのか」を意識しながら聞いてみる。こうした小さな積み重ねが、話すことの安定感を少しずつ高めてくれます。
うまく話せた日の再現パターンを自分なりに記録しておくのも有効です。「準備の段階で理由を書き出した」「朝に一人で声に出して練習した」など、自分のパターンが見えてくると、コンディションに左右されずに話せるようになっていきます。
話し方の上達は、気合いや一時的な集中力では続きません。だからこそ、自分なりの仕組みをつくって再現性を高めることが、長期的な成果につながります。
場面別に変わる話し方トレーニング
話す内容を整理し、伝える順序を整える力が身についてくると、実際の場面でも「少し話しやすくなった」と感じられるようになります。ですが、ここからもう一段上の成果を出すためには、話す場面ごとに構成や意識を変えることが必要です。
たとえば、人前に出ると緊張してしまうときと、会議でプレゼンをするときでは、準備の仕方も伝え方も変わってきます。自分の考えを伝えるだけでなく、相手の状況や目的に合わせて話し方を調整することで、伝わり方の質が大きく変わっていきます。
この章では、「緊張しやすい」「営業やプレゼンが苦手」「ビジョンをうまく語れない」「お客様とうまく意思疎通ができない」といったシーン別の悩みに応じて、構造的に話すための視点と工夫をお伝えしていきます。
自分に合った話し方の設計を見つけるヒントとして、ぜひ活用してみてください。
緊張しやすい人こそ、呼吸と構造を整える

人前に出ると、頭が真っ白になる。言葉が出てこない。そんな場面では、気持ちを落ち着けようとしても、うまくいかないことが多いものです。これは「性格」や「慣れ」の問題ではなく、身体と頭の両方が同時に混乱している状態だと言えます。
まず整えたいのが呼吸です。緊張しているとき、多くの人が「うまく吸えていない」と感じていますが、実はその前に「しっかり吐けていない」ことが問題です。吐き切らない限り、十分に吸うことはできません。ゆっくりと口から息を吐き切ることを何度か繰り返すだけで、呼吸の支えが安定し、声も出しやすくなっていきます。
もう一つ大切なのが、話す内容の構造を事前に決めておくことです。緊張しているときは、考える力が落ちています。だからこそ、当日その場で考えるのではなく、話す順序だけは決めておく。たとえば「最初に結論を言って、次に理由、その後に具体例を入れる」と決めておくだけでも、混乱をぐっと減らすことができます。
緊張しない話し方を目指すより、崩れにくい話し方を身につけること。呼吸と構造、この2つを整えることで、どんな場面でも落ち着いて話すための土台が育っていきます。
営業・プレゼンでは、論理だけでは響かない

営業やプレゼンのように相手を動かすことが目的の場面では、論理だけでは届かないケースが多くあります。
もちろん、話の内容が整理されていないと、そもそも相手には伝わりません。そのうえで求められるのが、「なぜ、あなたがその提案をしているのか」「どんな思いで話しているのか」といった、話し手の温度感や背景です。つまり、構造だけでなく感情の設計も必要になるのです。
たとえば、PREP法の中に、自分の実体験や顧客の事例を組み込んでみる。それだけでも、相手が「自分ごと」として受け取りやすくなります。提案の内容にストーリーが加わることで、聞き手の理解や納得に感情的な引っかかりが生まれるからです。
営業やプレゼンで成果を出す人は、「伝える順番」だけでなく「伝える温度」にも意識を向けています。自分の体験や相手の立場を想像しながら話す習慣をつけることで、言葉の説得力が自然と高まっていきます。
経営者に求められる「ビジョンの語り方」

営業やプレゼンのような説得の場面を超えて、さらに高い視座が求められるのが経営者の言葉です。何を成し遂げようとしているのか。どこに向かう組織なのか。それを言葉にすることは、単なる情報伝達ではなく、組織の意志を共有する行為です。
ビジョンを語るうえで重要なのは、どんな社会を実現したいのか。なぜそれが必要なのか。その実現のために今どんな取り組みをしているのか。といったWhyを整理すること。Whyを整理して、順序だてて説明することが、組織の中での納得や行動につながっていきます。
また、経営者の話には必ずその人自身の言葉が必要です。他人の文章を借りて話すのではなく、自分の体験や信念を交えて語ることで、言葉に体温が生まれます。理念をかたちだけで語るのではなく、自分の中から出てきた言葉として届ける。それが聞き手の感情を動かす力になります。
日常のコミュニケーションでも、こうした練習は積み重ねることができます。たとえば社内ミーティングの中で、少しだけ長いスパンの視点から話してみる。自分の言葉で、未来の姿を描いてみる。そうした小さな試みの積み重ねが、経営者としての伝える力を育てていきます。
顧客対応で成果を出す、会話の型とは

経営者がビジョンを語る場面とは対照的に、顧客対応の場では、相手の感情や状況にすばやく寄り添う力が求められます。
顧客対応で特に大切なのは、話す順番よりもまず「相手の話をどう受け止めるか」です。たとえば、こちらが先に説明を始めるのではなく、相手の状況をしっかりと聞き取る。そのうえで、確認すべき点を問い直し、共感や理解の姿勢を見せる。そして最後に、必要な情報を整理して伝えるという順序です。
このように、話す前にまず相手の話を整理することで、会話は自然とスムーズに進んでいきます。相手の感情を先に受け止める姿勢が、安心感と信頼につながり、結果として提案や対応も受け入れられやすくなります。
まとめ
話し方トレーニングの本質は、発声や滑舌といった表面だけでなく、思考を整理し、相手が聞きたい順に伝える構造を身につけることにあります。
呼吸で土台を整え、滑舌とスピードを整備し、型(PREP)で順序を固定化する。この流れを日々の仕組みに落とし込めば、緊張しても崩れにくい再現性のある話し方が育ちます。
結果として、①人前での自信、②ビジネスでの信頼、③日常の誤解減少という三つの成果が積み上がります。大切なのは「気合い」ではなく、毎日の小さな仕組み化です。
ぜひ、本記事を参考に話し方トレーニングを実施していただき、仕事、プライベートを充実したものに変えてくださいね。